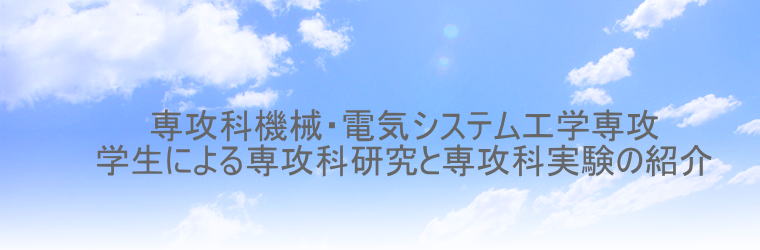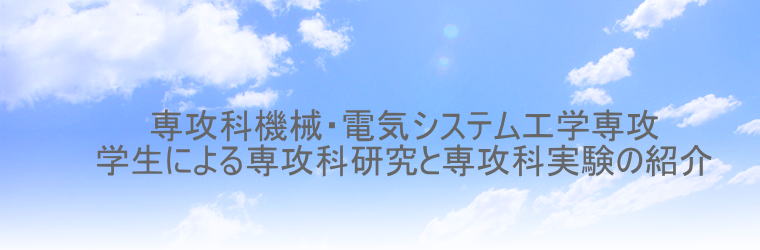|
|
| 自立型ロボットの製作と制御 |
自動化・省略化した生産活動には動作機構部とセンシング技術を併用したメカトロニクスに関する技術がとても重要です。この実験では比較的簡易に動作プログラミングを行うことができるロボット(レゴマインドストームNXT)を用い、メカトロニクスの基礎を学ぶことを目的としました。ソフトの基本的な使用法を習得した後、「本校低学年に機械工学への興味を持たせる」ことを目的としたロボットのデモンストレーションの内容(ロボットの動作)について企画・立案して実施・評価を行いました。
予備知識:数値制御、メカトロニクスなど |
レゴマインドストームNXT本体には超音波センサ、光センサ、音センサ、タッチセンサの4つのセンサと、3つのサーボモータが取り付けられています。ここではまず、それらを用いたプログラム例を参照してロボットを実際に動かしてみます。
NXTでは、プログラミングに複雑な言語を用いるのではなく、動作内容が抽象化されたアイコンを用いることで、簡単にプログラミングが組めます。 |
 |
| 「本校低学年に機械工学に対する興味を持たせるⅠ」というテーマのもと、ロボットを使用して機械工学により興味を持ってもらうにはどうすればよいかということを企画・立案しました。アイデアの発想の段階でマインドマップを使用し、前のテーマで学んだ基本動作プログラムの内容を組み合わせて1分程度のデモンストレーション動作をプログラミングしました。 |
 |
ここではNXT内でより複雑なプログラミングを行うためのデータハブの概念と、ロボットと人間の双方向的なやり取りが可能な教示やユーザーインターフェイスについて、プログラム作成を通して学びました。
データハブ:センサの読み取り値やさまざまな演算により算出された値を関数としてプログラム内でやり取りすることができます。
教示:人間が指示した動作をロボットになぞらせることを言います。
ユーザインターフェイス:人間が外部からロボットに指示を与えるための機構です。(右の図がプログラム例) |
 |
③で学んだ内容を盛り込んで、参加型のイベントについて企画・立案し、その全体像についてコンセプトマップを作成しました。 |
 |
プログラムに関しては苦手意識があったのですが、レゴNXTではアイコンを用いてプログラムを作成していくため、楽しみながらプログラミングができました。また変数の概念も図式的に捉えることができ、プログラムに関する理解も向上したように思います。
簡単にプログラムが組めるとは言いつつ、応用次第で複雑なプログラムを作成することができます。企画・立案に際して作成したプログラムはシンプルで直球勝負になってしまった部分があるので、こういった応用的な使用方法を盛り込んでもう少しひねりの利いたものにしたかったです。 |
|
|